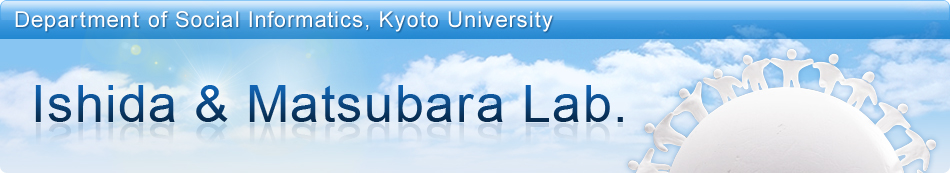田仲 理恵
(2006年3月学部卒業,2008年3月修士課程修了)
NEC C&Cイノベーション研究所/研究職
2005年4月,4回生で念願の配属となって以来,3年間を石田研で過ごしました.
学部では,社会的インタラクションプラットフォームFreeWalk/Qを使って,仮想都市の中で複数の相手に同時に対応できる対話エージェントのメカニズムを考えていました.修士では言語グリッドプロジェクトに参加し,複数の機械翻訳を接続した際に途中で訳が変わっていってしまう問題の解決に挑みました.
現在は研究所で,30年後の未来を考える研究に取り組んでいます.研究所が立ち上がったばかり,私も配属されたばかりで手探り状態ですが,石田研で学んだエージェントや連携の知識をベースに何か面白いことができないかな,と模索しているところです.
石田研では非常に様々な体験をさせていただいて,3年間があっという間に過ぎ去ったように思えます.学会などでの発表の場も幾度もいただきましたし,プロジェクトに参加して皆と一緒に何かを作り上げていく実感を得ることもできました.社会と繋がっている,動かしていくという実感が欲しい方にとっては,有意義な研究室生活を送ることができる場所だと思います.お世話になった石田先生と研究室の皆様に感謝するとともに,これから研究室を盛り上げていく学生さんたちのご活躍に期待します.

松村 郁生
(2006年3月学部卒業,2008年3月修士課程修了)
日本アイ・ビー・エム(株) 東京基礎研究所/主査研究員
私は学部と修士で合わせて3年間,研究室にお世話になりました.
現在はIT企業の研究員として社会人1年目をスタートしたところです.私が研究室に配属された当時,言語グリッドプロジェクトが立ち上がりつつありました.NICT,和歌山大学,NPOなど様々な組織の方と協調しながら作業を進めていく姿は,一般的な研究室に対して抱いていた閉鎖的なイメージと,良い意味でかけ離れたものでした.そんな環境の中で私は,事前に性質が予測できないようなXML Webサービスの通信を高速化する手法の研究に携わり,この内容は翌年アメリカの国際会議で発表をしました.都合により単身で1週間シカゴに出張し,分野の最先端に触れ,研究発表をし,さらに当地の観光もできたことはとても楽しく,よい経験となりました.
その後は研究室のメンバーなどと共に,Webサービスの合成プラットフォームに関するプロジェクトをIPAの「未踏ソフトウェア創造事業」に申請し採択されました.予算を頂いてチームを組み,ソフトウェアを開発し結果を発表する過程で,技術を人々に利用してもらうことの難しさとやりがいを学ぶことができました.
石田・松原研究室では,主体的にものごとを考えアイデアを提案することで,様々な道が開かれると感じます.後輩のみなさんには是非そうしてチャンスをつかみ,成長してほしいと思います.

椎名 宏徳
(2006年3月修士課程修了)
富士通株式会社
石田研究室には,修士課程の2年間在籍し,仮想空間のマルチエージェントシミュレーションを現実空間の避難訓練に組み合わせて,大都市での避難誘導訓練を実施する研究を行いました.もともと「動くものを作りたい」という希望を持っていたため,GPS付の携帯電話を持ったユーザと仮想空間のエージェントを誘導するためのシステムを開発し,被験者を集めて実験を行いました.実験では,自分の開発したシステムが実際に使用されたうえにテレビや新聞の取材を受け,貴重な体験をすることができました.
修了後は企業に就職し,社会インフラを支えるミドルウェアの開発業務を行っています.研究室でシステムを開発した経験は開発の現場でも役に立っています.石田研究室では,純粋なエージェント技術の研究だけでなく,私のようにエージェント技術を活用したシステムを開発して社会貢献を目指す研究を行うこともできます.自分に合ったやり方で,さまざまな形の研究ができる研究室です.
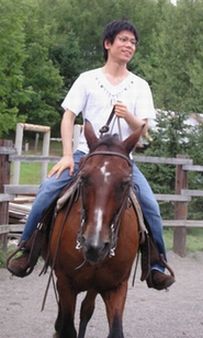
杉本 悠樹
(2003年3月学部卒業,2005年3月修士課程修了)
西日本電信電話株式会社
エージェントを軸として,学部時代はQとXML Webサービスを,院では機械学習,仮説推論を扱っていました.人工知能をやりたいと石田研に入り3年間,なんだかんだで好きなことを学ばせていただいたと思っています.思い出と言えば色々あるのですが,初めてSchemeに触れたときに,その美しさに衝撃を受け,魅了されてしまったことが,印象的な思い出です.周りに共感してくれる人がいないことが悩みですが,大きく価値観を変えさせられました.
現在,社内システムの開発を担当しています.要件定義や仕様決定などの上流工程のみを担当するのですが,テクニカルな部分の理解や,プレゼン・発表の機会などに,大学時代,主に研究室で培った知識や経験,論理的な思考方法などが生きてくることがあり,意外なつながりを感じることがあります.
自分自身は修士で就職しましたが,それでも学問の深淵の一端を垣間見ることが出来たと思います.是非深い知識や思想に触れ,大いに驚いてください.京大はそれを提供してくれる人材の宝庫だと思います.
深田 浩嗣
(1999年3月学部卒業,2005年3月修士課程中退)
株式会社ゆめみ 代表取締役社長
こんにちは,石田研OBの深田です.修士課程に進んだものの,修士1年の冬(当時2000年1月)に何を考えたか同級生と3人で起業し,以来そのまま現在に至り株式会社ゆめみの代表を務めています.
修士時代の思い出はと言えば,夏休みのときに石田先生のご紹介でシリコンバレーに3ヶ月ほどインターンに行かせて頂いたことがこの起業にも大きな影響がありました(そんなはずではなかった・・・!と先生は苦笑いされていらっしゃるかもしれませんが).貴重な経験をさせて頂いたと共に,現在でもその時に出会った方々とのお付き合いが続いており,いいご縁を頂戴したと大変感謝しています.
学生時代に起業した会社経営を続け,現在は50名ほどの規模になっています.個人的には情報学とは程遠い仕事が中心ですが,社会に情報学を役立てるということを実践したいという創業の思いは今も変わらず生き生きと胸にあります.
このような道を敢えて選択しようという奇特な方はあまりいらっしゃらないかとは思いますが,やや道を踏み外している僕のような人間でもいまだに快く石田先生はお付き合い下さっています.
エネルギッシュに生きたい!と思われる方は一度石田研のドアを叩いてみてはいかがでしょうか?
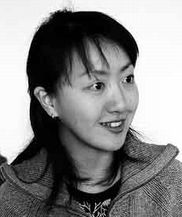
安岡 美佳
(慶應義塾大学文学部卒業,2003年3月修士課程修了)
IT University of Copenhagen / Ph.D Candidate
石田研究室が中心となって進めていたデジタルシティ・プロジェクトに魅せられ,2001年に慶応義塾文学部からの理転受験.結果,運良く石田研に迎えられ,2年間の修士生活を過ごした.この間,デジタルシティ及び異文化協調作業支援プロジェクトに従事した.研究室の他メンバーに比べ,私の計算機科学の知識は明らかに劣っていたが,2年間の修士研究を充実させることができたのは,教授の指導のもと,将来を見据えた興味深くかつ国際的にも意味のあるプロジェクトが巧みにデザインされたこと,才能豊かな研究室の教官,諸先輩方,後輩に囲まれて切磋琢磨しつつも助け合うという古き良き研究室文化に支えられたという2点が大きい.当時は気がつかなかったが,数カ国,数カ所での研究生活を経て石田研の研究環境は非常に恵まれていたと改めて思う.
現在,私は,海外での博士取得を目指す学生対象の私設の奨学金を得て,デンマークで博士過程取得を目指している.博士研究では,修士課程に取りかかり始めた異文化協調作業を支援する計算機のデザインとは,というテーマを変わらず追い続けている.
研究の世界を目指す後輩たちには,自分の研究を充実させるためにも,研究に最適な場に身を置く重要性を理解し,巨人の肩を借りながら,自らの目指す研究を見つけて欲しいと願っている.

梁 連秀
(2001年3月修士課程修了)
株式会社 東芝 ソフトウェア技術センター
先端ソフトウェア開発担当/主務
修士のときは人と観光案内エージェント間の会話を蓄積しモデル化する研究をしました.当時注目されていた「デジタルシティ京都」プロジェクトでは3D京都をインターネット上に作ったりもしました.その後(株)東芝に就職しソフトウェア技術センター部門で勤務しています.今は海外研修でスタンフォード大学に赴任,HCIグループでUIデザインツールの研究をしています.長らくの実践者生活からアカデミアン生活に戻り再び研究活動の素晴らしさと難しさを味わっています.研究者は何をするのか決めることが一番難しいとよく言われます.自分のビジョンや問題意識から何をするか決めた後もそれを具体化し,価値を求め,モノを作り,結果を検証し,世界に認められるまでは壮大なドラマが繰り広げられることになります.企業の研究機関ではその過程で事業戦略,実用性などの要因が働きますが大学ではより自由な環境で自分の信念を成し遂げることができると思います.

小久保 卓
(1999年3月学部卒業,2001年3月修士課程修了)
ノキアシーメンスネットワークス株式会社,事業戦略統括(Head of Strategy & Business Development, Japan)
石田研究室の研究分野は幅広く,一見分かりにくく感じるかもしれませんが,逆に他の分野と関連付けることも可能であり,興味ある分野を研究テーマに出来る研究室だと思っています.実際に私もそれまでの研究室のテーマには含まれていなかった「特定分野向け検索エンジン」の研究をさせていただきました.
現在は,研究テーマとは関係ない(技術的知識はかなり役立っていますが),「新たな通信インフラ導入の戦略策定」や「サービス開発の投資判断」などの業務を行っています.しかし,そこで必要とされる能力は研究室時代に基礎を鍛えていただいたと思っています.というのも,石田研究室は外部組織や企業との接点・プロジェクトが多く,様々な年代・バックグラウンドの人とコミュニケーションをとり,チームで何かを完成させるという経験を積むことが出来たからです.
自らの反省も込めたアドバイスですが,研究の中身そのものだけでなく,一歩引いた視点で作業の全体像や各プロセスの必要性も意識してみてください.最近世の中では「問題解決力」等が注目されていますが,一つの事象に深く取り組む研究過程は,それらと非常に似ており,研究内容と同様に今後に活かせると今になって感じております.
皆さんのご活躍を期待しております.
山内 裕
(1998年3月学部卒業,2000年3月修士課程修了)
Palo Alto Research Center / Member of Research Staff II
私が情報工学を目指したのは,高校生の時に,Xerox Palo Alto Research Center (PARC) についての本を読んだことが始まりでし た.ウィンドウシステム,イーサネット,マウス,WYSIWYGエディタなどの発明だけではなく,それらの発明から会社を起こし,成功した人々がいることに魅かれました.その後,京大で「計算機」について学び始めたのですが,その中で魅かれていったのが,コンピュータと社会との接点でした.石田先生が社会情報学 専攻を立ち上げられることになったのです.中でも,企業などの組織に関する学問(組織論)に魅かれ,米国のビジネススクール (UCLA)の博士課程に入学しました.そして,情報工学から遠ざかったつもりだったのですが,奇妙なことにPARCに出入りするようになりました.というのは,80年代前半からPARCは職場や組織の研究で先駆者となっていたからです.高校生のときに憧れてから10年,方向性を変えながら,元に戻ったというわけです.
ところで,PARCは今世紀に入ってから変貌を遂げつつあります.2008年8月に社長がその変化を振り返り,新しいPARCを宣言しました.Xeroxから独立の道を探り始め,2002年には別会社に組織化されました.他のパートナーに価値のある研究は,協業を通してそのパートナーのビジネスを助けるというビジネスモデルを進化させました.印刷やコンピュータを離れ,バイオ技術,クリーンテックなどの新分野にも進出してきました.現在,日本の会社も含め,様々なパートナーとプロジェクトを進めています.ソーラー技術のSolfocus,Microsoftに買収されることになった自然言語サーチのPowersetなどのスタートアップを通じたビジネスも成功してきています.
振り返ると,革新的な研究とそれをベースにビジネスで価値を作り出すという,高校生のときに憧れたイメージと重なります.研究者の多くは,自分の研究で新しいビジネスを起こす野心を持ち,それを会社が後押しします.同時に,Web2.0,Cloud Computingに代表されるように,情報工学の研究そのものが,純粋な技術だけではなく,社会とビジネスのコンテキストでの応用へとシフトしています.金融業界では,情報工学の技術が直接リターンへと繋がります.これほど人間,社会,ビジネスに密着し,応用範囲の広い学問分野はないと思います.10年後何が流行っているかは誰も予想できませんが,情報工学は社会やビジネスの変化と共に,さらなる進化を遂げていくでしょう.